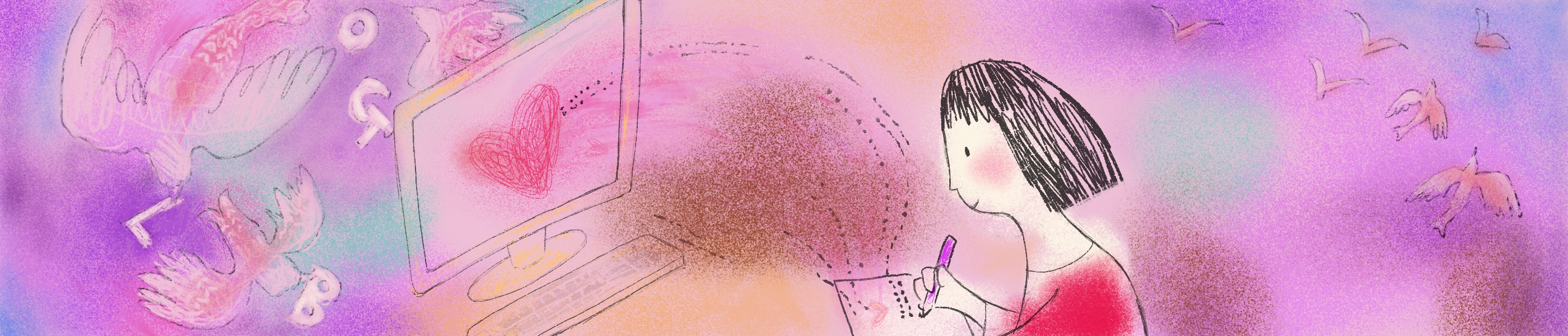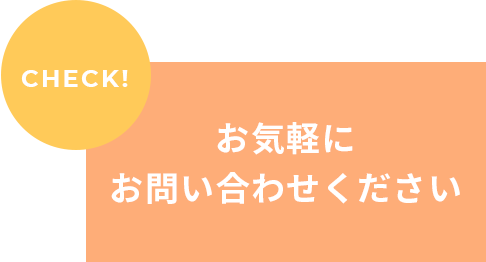Blog ブログ
高学年(小学6年生)への読み聞かせボランティア 10分で読んだ絵本 2冊
読み聞かせボランティアとして
約16年
お邪魔している小学校があります。
今年度初の読み聞かせ。
6年生のクラスに絵本を読みに行ってきました。
よく
「高学年にどんな絵本を読んだらいいのかわからない」
というご質問をいただくので
わたしが6年生に読んだ絵本を参考までにご紹介します。

時間は10分です。
児童たちは、コの字に机を置いて、お互いの顔が見えるように座ってました。
黒板には、「25分から読み聞かせ」と書いてありました。
先生が、「どうぞ」と声をかけてくれたので、教室に入りました。
みんな一生懸命ついてくるように聞いていました。
読み終わると、一瞬、シン となりました。
「これ、なんだかわかった?」
「最後の文字でしりとりしてる!」
「そうだね。二つずつのしりとりで、しかも文章だね。
じゃあ、この本には全部は18個のことばのこばこがあるんだけど、何番がいいですか?」
「36!」「18!」「13!」「20!」
「じゃあ、みんながよく知ってる 上から読んでも下から読んでも同じ言葉ってどんなのがありますか?」
「トマト!」「新聞紙」「こばこ」「竹藪焼けた」
「よし、じゃあいくよ」(聞いておきながら「ことばのこばこ③」」
前半は、知ってるのだから、うん、うん、頷きながら聞いていたけど、
どんどん、真剣な表情に。下から読んでも本当に同じ言葉なのか確かめるように。
読み終わると
「おー!」という声。
そして、
「『こばこ』がない」という鋭いツッコミも。ホントだね。
「こんなふうに、ことばのこばこが18個入ってます」
「面白い」との声。
「じゃあ、次はこちら。ことばのこばこ13」
「いち!!」と嬉しそうな声。
今回は、3つだけ紹介しました。
「じゃあ、違う絵本を読んでもいいですか?」
「いえ〜い」
「まだ時間大丈夫ですか?」
「大丈夫、大丈夫」
「じゃあ、みんな6年生だから知ってるかもしれないけど、世界で一番古い子どものための本はどこの国で作られたでしょうか?」
「日本!」「モンゴル!」
「みんなは、びっくりするかもしれないけど、昔は子どものための本なんてなかったんだよね。
でも、唯一、本を読める子どもがいたの。
それは、王様の子ども。」
「あー!」「はらぺこあおむし?」
「ううん、もっとずっと昔。(西暦200年ですって)
インドの『パンチャタントラ』という王様の子どものためのお話が元になった絵本です。」
『あおいやまいぬ』
(マーシャ・ブラウン 瀬田貞二 瑞雲舎 1999年4月)
「やまいぬ?」
「ジャッカルのことだって」
こんなふうに、この絵本の背景をちょっとだけお話しして読んでみました。
ちなみにこちらの絵本は、『あおいジャッカル』と改題、小宮由さんの新訳で2017年に刊行されています。
「はげやま?」
「へー」
「あい?」
「ちょっとかっこいい」
「さらまもり」
などと、声が上がっていましたが、次第にシンとなりました。
読み終わると拍手をいただきました。
「はい、では時間になりましたので、これで終わりにしたいと思います。
今日も一日、お勉強がんばってください」
こんなふうに、わたしは子どもたちとのやり取りを楽しみながら絵本を読むのが好きです。
また、自分にとって挑戦だなという絵本は、「どうしたら聞く気になってくれるかな」と考えます。
『あおいやまいぬ』は、読み聞かせ初挑戦でした。
絵本の解説みたいなことは邪道かもしれないけれど、「これが王様になる子どものためのお話なのか」「どのあたりが?」と考えながら聞いてもらうのも、6年生だったらいいのかなと思いました。
また、「ごもんのすけ」「かさかざしのこしょう」など、わかりにくいかもしれない言葉もありますが、読んでいる最中に説明はしません。
その言葉は聞き取れるように、ゆっくり読むことは意識しています。
絵を見たら、なんとなく当たりをつけることはできるでしょう。
最高学年が始まった彼ら。
王様にいずれなる子どもへの物語。
なにか、ぼんやりとしたものでも、受け取ってもらえたらいいなと思いました。
ちなみに、この2冊は瑞雲舎の井上みほ子さん講演会の日に購入しました。
【報告】瑞雲舎 井上みほ子さん講演会 編集者として紙の本を生み出す人のお話
【著書】 『やってみる? 読み聞かせボランティア』(電子書籍&ペーパーバック)
約16年
お邪魔している小学校があります。
今年度初の読み聞かせ。
6年生のクラスに絵本を読みに行ってきました。
よく
「高学年にどんな絵本を読んだらいいのかわからない」
というご質問をいただくので
わたしが6年生に読んだ絵本を参考までにご紹介します。

時間は10分です。
児童たちは、コの字に机を置いて、お互いの顔が見えるように座ってました。
黒板には、「25分から読み聞かせ」と書いてありました。
先生が、「どうぞ」と声をかけてくれたので、教室に入りました。
目次
6年生にどんなふうに絵本を読んだか
「おはようございます」
「あー!! なんだっけ、なんだっけ」(とわたしの名前を思い出そうとしてるらしき男子)
「上甲です」
「あー!! そうだった、そうだった」
「6年生になった皆さんに会うのは今日が初めてですね。
5年生のときには会ったことがあると思いますが。
さて、今日は絵本を持ってきました」
「いえ〜い!!」
「やった〜」
「では、最近わたしが買った絵本を紹介したいと思います。こちらです」
『ことばのこばこ』
(和田誠 瑞雲舎 1995年7月)
「和田誠さんという人が作った絵本です」
「まこと?」
「知ってる?」
この絵本には、ことばあそびが見開きに1つずつ、全部で18の「ことばのこばこ」がありますので、まず、最初に「ことばのこばこ①」を読みました。
(以下引用)
くも の むこうに なにが ある
あるぷす の ゆき あるの かな
かなだの もりか はらっぱか
ぱかぱか うまも かけていく
(中略)
てるてるぼうず ぶらさげながら
がらすの そとを みるたびに
たびに でたいと おもうよ ぼくも
(引用ここまで)
みんな一生懸命ついてくるように聞いていました。
読み終わると、一瞬、シン となりました。
「これ、なんだかわかった?」
「最後の文字でしりとりしてる!」
「そうだね。二つずつのしりとりで、しかも文章だね。
じゃあ、この本には全部は18個のことばのこばこがあるんだけど、何番がいいですか?」
「36!」「18!」「13!」「20!」
「じゃあ、みんながよく知ってる 上から読んでも下から読んでも同じ言葉ってどんなのがありますか?」
「トマト!」「新聞紙」「こばこ」「竹藪焼けた」
「よし、じゃあいくよ」(聞いておきながら「ことばのこばこ③」」
(以下引用)
こねこ
とまと
しんぶんし
きつつき
(中略)
わたしねんねしたわ
たったいままいたつた
たいふうごうごうふいた
(引用ここまで)
前半は、知ってるのだから、うん、うん、頷きながら聞いていたけど、
どんどん、真剣な表情に。下から読んでも本当に同じ言葉なのか確かめるように。
読み終わると
「おー!」という声。
そして、
「『こばこ』がない」という鋭いツッコミも。ホントだね。
「こんなふうに、ことばのこばこが18個入ってます」
「面白い」との声。
「じゃあ、次はこちら。ことばのこばこ13」
(以下引用)
いちわでも にわとり
にどたべても さんどいっち
さんにん いても しじん
よじに きても ごじら
(中略)
きゅうかいでも とう
じゅっかい ほえても わん
(引用ここまで)
「いち!!」と嬉しそうな声。
今回は、3つだけ紹介しました。
「じゃあ、違う絵本を読んでもいいですか?」
「いえ〜い」
「まだ時間大丈夫ですか?」
「大丈夫、大丈夫」
「じゃあ、みんな6年生だから知ってるかもしれないけど、世界で一番古い子どものための本はどこの国で作られたでしょうか?」
「日本!」「モンゴル!」
「みんなは、びっくりするかもしれないけど、昔は子どものための本なんてなかったんだよね。
でも、唯一、本を読める子どもがいたの。
それは、王様の子ども。」
「あー!」「はらぺこあおむし?」
「ううん、もっとずっと昔。(西暦200年ですって)
インドの『パンチャタントラ』という王様の子どものためのお話が元になった絵本です。」
『あおいやまいぬ』
(マーシャ・ブラウン 瀬田貞二 瑞雲舎 1999年4月)
「やまいぬ?」
「ジャッカルのことだって」
こんなふうに、この絵本の背景をちょっとだけお話しして読んでみました。
ちなみにこちらの絵本は、『あおいジャッカル』と改題、小宮由さんの新訳で2017年に刊行されています。
「はげやま?」
「へー」
「あい?」
「ちょっとかっこいい」
「さらまもり」
などと、声が上がっていましたが、次第にシンとなりました。
読み終わると拍手をいただきました。
「はい、では時間になりましたので、これで終わりにしたいと思います。
今日も一日、お勉強がんばってください」
こんなふうに、わたしは子どもたちとのやり取りを楽しみながら絵本を読むのが好きです。
また、自分にとって挑戦だなという絵本は、「どうしたら聞く気になってくれるかな」と考えます。
『あおいやまいぬ』は、読み聞かせ初挑戦でした。
絵本の解説みたいなことは邪道かもしれないけれど、「これが王様になる子どものためのお話なのか」「どのあたりが?」と考えながら聞いてもらうのも、6年生だったらいいのかなと思いました。
また、「ごもんのすけ」「かさかざしのこしょう」など、わかりにくいかもしれない言葉もありますが、読んでいる最中に説明はしません。
その言葉は聞き取れるように、ゆっくり読むことは意識しています。
絵を見たら、なんとなく当たりをつけることはできるでしょう。
最高学年が始まった彼ら。
王様にいずれなる子どもへの物語。
なにか、ぼんやりとしたものでも、受け取ってもらえたらいいなと思いました。
ちなみに、この2冊は瑞雲舎の井上みほ子さん講演会の日に購入しました。
【報告】瑞雲舎 井上みほ子さん講演会 編集者として紙の本を生み出す人のお話
【著書】 『やってみる? 読み聞かせボランティア』(電子書籍&ペーパーバック)
高学年への読み聞かせボランティア関連記事
今まで高学年のクラスで読み聞かせボランティアをしたことについて書いたブログ記事を参考までにリンク貼っておきます。
2月 小学6年生に読み聞かせ 大人になりかけていく彼らへのエール